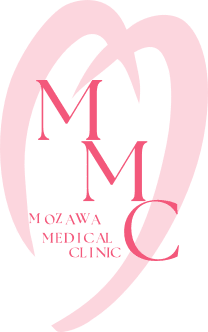糖尿病が疑われる際の診察所見と実際の診断に用いられる検査方法について分かりやすく解説していきます。
① 診察所見
糖尿病が長期間続くと神経障害や血流障害による特徴的な所見が現れることがあります。わかりやすい身体所見としては以下をチェックしていきます。
-
腱反射の低下
初期症状で出やすい末梢神経障害のサインとして診察します。特にアキレス腱反射(かかと部分を軽く叩いたときの反応)が低下していると、糖尿病性神経障害が疑われます*¹。
-
振動覚の低下
128Hzの音叉の振動を足趾(足の指)に当てて振動を感じるかを確認します。振動を感じにくい場合は糖尿病性末梢神経障害の可能性があります。
② 糖尿病の診断方法
1. 血液検査
血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)を測定し、診断基準を満たすかどうかを確認します。血糖値は直近の食事の内容やタイミングで幅は出てきますがHbA1cは約2か月の血糖値の平均値を求められるので診断の軸として重要になります。
診断基準は以下です。
診断基準(糖尿病型)
血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)を測定し、診断基準を満たすかどうかを確認します。
【※下記のいずれかが基準値を満たし、別の日の再検査でも確認できた場合は糖尿病と診断されます*²。】
| 検査項目 | 診断基準(糖尿病型) | 補足 |
|---|---|---|
| 随時血糖 | 200mg/dL以上 | 食事時間に関係なく測定 |
| 空腹時血糖 | 126mg/dL以上 | 10時間以上絶食後の血糖値 |
|
75g OGTT (ブドウ糖負荷試験)2時間後 |
200mg/dL以上 | 糖負荷後の血糖変動を確認 |
| HbA1c | 6.5%以上 | 過去1〜2か月の平均血糖値を反映 |
2. 尿検査
糖尿病では血糖値が高くなりすぎると腎臓での再吸収が追いつかず、尿に糖が漏れ出します(尿糖陽性)。また糖尿病性腎症の進行を評価するために尿中アルブミンの測定も行います。糖尿病初期では尿中に微量のアルブミンが検出されることがあり、これらの適切な評価が早期診断と介入につながります。
| 検査項目 | 意義 |
|---|---|
| 尿糖 | 陽性なら高血糖の可能性 |
| 尿中アルブミン(微量アルブミン尿) | 糖尿病性腎症の早期発見に重要 |
3. 糖尿病とインスリン抵抗性:Cペプチドを用いた評価
糖尿病の診断や治療方針を決める際にその方の「インスリン抵抗性」と「インスリン分泌能」の評価が重要になります。それを評価することでその方にあった食事・運動指導はもちろん処方する薬や注射製剤の組み合わせもかわってくるからです。「Cペプチド(C-peptide)」は体内のインスリン産生能力を評価する上で有用な指標です。ここではインスリン抵抗性のメカニズムとCペプチドの役割について少しだけ掘り下げ解説します。
① インスリン抵抗性とは?
「インスリン抵抗性(insulin resistance)」とは膵臓からインスリンが十分に分泌されているにもかかわらず、肝臓・筋肉・脂肪組織での糖の取り込みや利用が低下してしまう状態を指します。その結果、血糖値が上昇し、膵臓はさらにインスリンを無理やり分泌することで何とかその場をしのごうと対応します。
- 主な原因
肥満(特に内臓脂肪の蓄積):脂肪細胞から分泌される炎症性サイトカインがインスリンの働きを妨げてしまいます。
慢性的な高血糖:高血糖が長期間続いてしまうとインスリンそのものの効果を鈍らせます。
遺伝的要因:家族歴がある場合、インスリン抵抗性を持ちやすい。
加齢:インスリン感受性が低下する傾向がある。
これらの要因でインスリン抵抗性が進行すると膵臓のβ細胞が疲弊してしまい、最終的にインスリン分泌量が低下する悪循環に陥ってしまいます。これが2型糖尿病の進行メカニズムの一つです。
② Cペプチド(C-peptide)とは?
Cペプチドは、膵臓でインスリンが生成される際に同時に分泌される物質です。インスリンと1:1の割合で産生され、体内で分解されにくいため、血中のCペプチド濃度を測定することで膵臓のインスリン分泌能力を高精度で推定できます*³。
また、Cペプチドは注射インスリンには含まれないため、インスリン注射をしている方の内因性インスリン分泌能力を評価するのにも役立ちます。
| 検査項目 | 意義 |
|---|---|
| 血中Cペプチド(空腹時) | 内因性インスリン分泌量の指標として評価 |
| 尿中Cペプチド排泄量 | 24時間のトータル尿内にあるCペプチド値からその方のインスリン分泌の総量を評価 |
③ インスリン抵抗性の評価方法
インスリン抵抗性の評価には、Cペプチドのほかに以下の指標も用いられます。
・HOMA-IR(インスリン抵抗性指数)
空腹時血糖値(mg/dL)× 空腹時インスリン(μU/mL)÷ 405
(2.5以上でインスリン抵抗性を示唆)
・HOMA-β(インスリン分泌能指数)
360 × 空腹時インスリン(μU/mL)÷ (空腹時血糖値-63)
(膵臓β細胞の機能を評価)
ここがポイント
最後の方に少し専門的な難しいお話しもさせていただきましたが、皆さんにお伝えしたいのは多くの血液検査項目や計算式から求められる指標を組み合わせて、一人一人の体質を把握することが重要であるということです。 そして血液検査での血糖値やHbA1cの評価が診断の決め手となる一方で、長期的な影響を評価するために神経障害(腱反射・振動覚低下)、眼底異常、腎機能のチェックも重要です。定期的な診察と検査がキーとなります。
- *¹ Vinik AI, et al. "Diabetic Neuropathy: Clinical Manifestations and Diagnosis." Diabetes Care. 2021.
- *² American Diabetes Association. "Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus." Diabetes Care. 2022.
- *³ Jones AG, et al. "C-peptide measurement in diabetes: Clinical applications and limitations." Diabetologia. 2021.