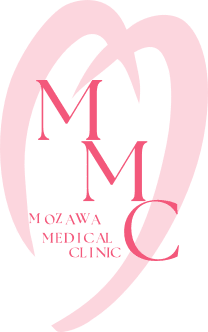呼吸器の全体像
私たちの体は 24 時間休まず酸素を取り込み、二酸化炭素を排出しています。 このガス交換を行うのが呼吸器系で、大きく「上気道」と「下気道」に分かれます。
- 上気道: 鼻・咽頭・喉頭
- 下気道: 気管・気管支・肺
鼻や口から入った空気は気管を通り、二股に分かれて左右の肺に流れ込みます。
肺の構造と役割
肺は左右一対のスポンジのような臓器で、数億個の「肺胞(はいほう)」と呼ばれる小さな袋でできています。
イメージ例
肺は「巨大なぶどうの房」と想像してください。茎(気管支)から枝分かれして房(肺胞)がぶら下がっており、その一粒一粒が酸素交換の現場です。 肺胞の表面積はテニスコート1面分にもなるとされ、私たちが常に呼吸しているガスを生理的に交換し、不純物などは取り除くようなフィルター効果も併せ持っています。 主に肺と気管支で構成される呼吸器は生命維持には必要不可欠であり、これらの異常は“長引く咳”や“動いたときに息苦しい、息切れ”、“痰が切れない”などの症状として現れ、時に重篤な健康問題に直結することが多々あります。
★ここから先では代表的な 気管支喘息 と 肺気腫(タバコ肺) について詳しく解説していきます。
気管支喘息
1. 気管支喘息の病態・原因
気管支喘息は、肺へ空気を運ぶ「気道(ホース)」が慢性的な炎症で狭くなる病気です。まるでホースに粘土がまとわりついて通り道が狭まり、水が流れにくくなるような状態です。
- - 炎症のしくみ:免疫細胞が過剰に働き、気道の粘膜が腫れ、平滑筋が収縮して呼吸が苦しくなる。
- - 原因例:アレルギー反応(花粉・ダニなど)/環境刺激(タバコ煙・大気汚染)/ストレス・感染症など。
- - 進行による変化:慢性炎症の結果、気道の構造が変形し、発作が起こりやすくなることもあります。
- GINA 2023 ガイドライン — Global Strategy for Asthma Management and Prevention(2023年更新) Global Initiative for Asthma - GINA
2. 分類と病型の多様性
喘息には様々なタイプがあります:
- - アレルギー性・非アレルギー性:免疫反応により発症するか否かで分けられます。
- - 年齢による分類:小児発症型/成人発症型など。
- - 重症度別:「間欠型」「軽症持続型」「中等症持続型」「重症型」。
3. 診断方法
- 問診・診察 — 夜間・早朝の咳込みや呼吸の苦しさの頻度を確認。特に聴診では息を吐くときに“ヒュー”というような高音の狭窄音が聴取できます。Wheezeといわれるこの音の聞こえ具合により喘息の管理状態も推測します。
- アレルギー検査・画像診断 — 他疾患との識別や合併・リスク評価。
4. 治療
治療は「内服薬」と「吸入薬」に大別されます。
内服薬
- ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA): 炎症を抑え軽度喘息のコントロールに使用。
- ステロイド(経口・点滴):重症発作時に一時的に用いるケースも。
吸入薬
主な吸入薬の種類:
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| ICS(吸入ステロイド) | 気道炎症の根本を抑える |
| ICS/LABA 合剤 | ICSに長時間作用型β₂刺激薬を追加して強力に制御 |
| ICS-Formoterol(ミックス製剤) | 日常+発作時にも対応 |
| LAMA 追加療法 | ICS/LABAでもコントロール不十分な時に追加検討 |
最近は多くの種類が合剤として1個に集約されたミックス製剤が注目され、利便性や治療効率も向上してきました。しかしながら、時には過剰となったり、漫然と安定期にも使用されているケースも散見されます。 適切なタイミングでその時の状態にあった吸入薬選びが大切です。
5. 咳喘息
風邪の後に長引く咳が、喘息の前段階である 咳喘息 に移行することが多くあります。
- ・主症状は「咳のみ」で喘鳴や呼吸困難がないが、炎症メカニズムは気管支喘息と共通しています。
- ・適切にコントロールしないと、通常の喘息へ進展するリスクがあります(約30〜40%)。
特に素因として小児喘息を患っていた方やアレルギー過敏性の方は相対的にリスクが高いといわれています。 長時間放置することで気管支内壁の炎症が長期化し、治療を開始しても効果が乏しく長い間咳で悩まれることもあります。 早めにご相談いただければと思います。
肺気腫(タバコ肺)
1. 肺気腫の病態・原因
肺気腫は肺の中の肺胞(酸素を取り込む小さな袋)が壊れて数が減り、空気の交換がしにくくなる病気です。
健康な肺は、まるで新しいスポンジのように細かい穴がたくさんあって弾力がありますが、肺気腫ではスポンジの穴が大きく合体し、硬くなってしまったような状態です。
病態のしくみ
肺胞の壁が破壊され、表面積が減少 → 酸素を取り込む能力が低下
弾力が失われて呼気がうまくできず、肺の中に空気が溜まりやすくなります(過膨張)。
主な原因例
- ・長期の喫煙(最大の危険因子)
- ・大気汚染や粉塵の吸入
- ・α1-アンチトリプシン欠損症(遺伝性)
- ・長年の慢性気管支炎など
進行による変化
酸素不足(低酸素血症)や二酸化炭素の貯留(高二酸化炭素血症)が進行し、全身の臓器に負担がかかります。
- GOLD 2024 — Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
2. 分類と病型の多様性
肺気腫は、破壊される肺胞の分布パターンで分類されます。
- - 中心小葉型:肺の中心部分(細気管支の周囲)から破壊が始まる。喫煙に多い。
- - 汎小葉型:肺全体に均一に障害が広がる。遺伝性(α1-アンチトリプシン欠損症)に多い。
- - 末梢小葉型:肺の外側部(胸膜直下)が優先的に障害される。自然気胸の原因になりやすい。
3. 診断方法
問診・診察
- ・長期の喫煙歴や慢性的な息切れの有無を確認。
- ・胸郭が膨らんだ「樽状胸」が見られることもあります。
肺機能検査(スパイロメトリー)
- ・1秒率(FEV1/FVC)が70%未満で閉塞性換気障害と診断。
画像診断(胸部CT)
- ・肺胞破壊の程度や分布が明確にわかります。
血液ガス分析
- ・酸素・二酸化炭素のバランスを評価し、重症度を判断。
4. 治療
肺気腫は一度壊れた肺胞を元に戻すことはできません。そのため進行を遅らせ、症状を軽減することが治療の中心になります。
薬物療法
| 薬の種類 | 作用 | 使用目的 |
|---|---|---|
| LAMA(長時間作用型抗コリン薬) | 気道を広げる | 息切れ改善 |
| LABA(長時間作用型β₂刺激薬) | 気道を広げる | 活動時の呼吸苦軽減 |
| ICS(吸入ステロイド) | 炎症を抑える | COPDと喘息の合併例に適応 |
| PDE4阻害薬 | 炎症抑制 | 頻回増悪例 |
非薬物療法
- ・禁煙(最も重要な治療)
- ・呼吸リハビリテーション(腹式呼吸・口すぼめ呼吸など)
- ・運動療法(筋力維持)
- ・酸素療法(在宅酸素療法:HOT)
5. 合併症と注意点
- ・急性増悪(感染や大気汚染が誘因)
- ・自然気胸(末梢小葉型で多い)
- ・肺高血圧症や右心不全(肺性心)
6. 日常生活の工夫
- ・無理のない運動で筋力を維持
- ・冬やインフルエンザ流行期はマスク・手洗いで感染予防
- ・栄養管理(過度なやせや肥満を避ける)
ここがポイント
肺気腫は、肺の「スポンジ構造」が壊れる病気です。禁煙と早期診断が進行を防ぐ最大のポイント。症状が軽いうちから治療と生活改善を始めることで、日常生活の質を守ることが可能です。