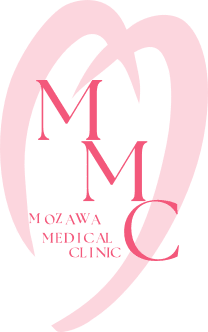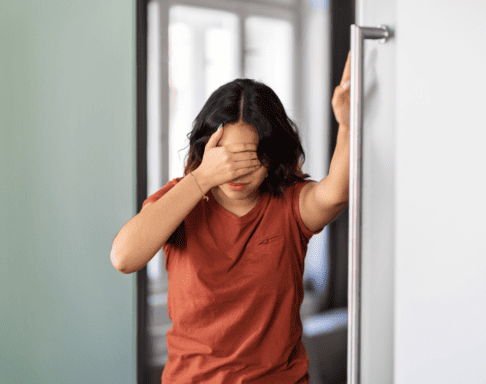貧血とは?
「貧血」とは血液中の赤血球やヘモグロビン(Hb)が不足し、体内に十分な酸素を運べなくなった状態を指します。単なる「血が薄い」というイメージを持たれがちですが、実際には 酸素供給の低下 が体のあらゆる臓器に影響を及ぼす重要な疾患です。
私たちの体は酸素がなければエネルギーを作り出せません。そのため、貧血は脳や心臓、腎臓など酸素を多く必要とする臓器にとって致命的な問題を引き起こす可能性があります。
よく診察していると起立性低血圧(いわゆる脳貧血)と混同している患者様が多くいらっしゃいます。自律神経が未熟な学生のころなどは校長先生の長い朝礼の話でバタバタと倒れてしまうのがこの起立性低血圧や自律神経失調などといわれる病態です。
脳に有効に血流をあたえる最低限の血圧が長時間の立位などでさがってしまい、気分不良や意識消失、めまいなどが生じます。
医学的な貧血とは‘血液の濃度’をさし、俗語である脳貧血とは‘血圧の調整の異常で一時的に脳への血圧が低下’してしまう病態です。
貧血の種類と原因
貧血にはさまざまな原因があります。当院では以下のタイプを鑑別することを大切にしています。
鉄欠乏性貧血
もっとも頻度が高く、特に女性に多い。月経過多や消化管出血、慢性的な鉄不足が原因となります。鉄欠乏に加えて月経量が多き場合はダブルパンチ状態となり血液が不足してしまいます。
慢性疾患に伴う貧血(腎性貧血など)
慢性腎臓病や炎症性疾患ではエリスロポエチン(造血ホルモン)が不足し、赤血球を作れなくなります。
巨赤芽球性貧血(ビタミンB12・葉酸欠乏)
栄養障害やアルコール多飲、胃切除後にみられます。
溶血性貧血
赤血球が壊されやすくなるタイプ。自己免疫や遺伝性疾患が原因。
再生不良性貧血など骨髄疾患
造血そのものが障害される重症のタイプ。
貧血の症状
患者さんが「ふらふらする」「立ちくらみがする」と表現されることが多いですが、それ以外にも多彩な症状があります。
- • 動悸・息切れ
- • 疲れやすさ、倦怠感
- • 集中力低下
- • 顔色が悪い
- • 爪の変形(スプーンネイル)や口角炎
これらは一見「年齢のせい」と思われがちですが、実際には貧血が背景に隠れているケースが多いのです。そのため当院では血液検査を提案することを心掛けています。
循環器内科の視点
貧血が心臓に与える影響私の専門である循環器領域では、貧血は心疾患にとって大きなリスク因子です。
① 心拍数・心拍出量の増加
貧血で血液中の酸素が減ると、体は少ない酸素を全身に届けようと(心拍)数を増やすことで代償します。そのため「動悸」を自覚しやすくなります。長期的には心臓に負担がかかり、心肥大や心不全を招くこともあります。
② 狭心症・心筋梗塞の悪化
酸素が不足する状態では、心筋への血流が少しでも減ると胸痛が起きやすくなります。狭心症の方では軽度の貧血でも発作が増えることがあります。心筋梗塞後の方にとっても、貧血は再発や予後悪化のリスクになります。
③ 心不全の進行
心不全患者さんにとって、貧血は「心不全増悪の悪循環」を作ります。酸素が足りず、さらに心臓が頑張り続ける → 心臓が疲弊 → 心不全が進む。この流れは多くの臨床研究でも明らかになっています。
糖尿病内科の視点
貧血と血糖コントロール糖尿病の患者さんにも貧血は重要な問題です。
① HbA1cの解釈への影響
HbA1cは過去1〜2か月の平均血糖を反映しますが、赤血球寿命に影響を受けます。鉄欠乏性貧血ではHbA1cが実際の血糖より高めに出ることがあり、逆に溶血性貧血では低めに出ることがあります。したがって、貧血があると血糖コントロールの評価を誤る可能性があります。
② 慢性腎臓病との関連
糖尿病腎症が進行すると腎性貧血が出現します。腎臓から分泌されるエリスロポエチンが減少するためです。これは糖尿病患者さんのQOL低下や心血管イベントリスク増加にも直結します。
検査・診断の流れ
当院では、まず血液検査で以下を確認します。
- • ヘモグロビン(Hb)
- • 赤血球数、MCV(赤血球の容積≒大きさ)
- • フェリチン(肝臓に貯蔵されている鉄の指標)
- • 網赤血球数(造血能の評価)
- • 腎機能、ビタミンB12・葉酸
これに加え、出血源が疑われる場合は消化器内視鏡や婦人科的評価を行うこともあります。
貧血の治療
全身・心臓への影響を考慮したアプローチ貧血の治療は単に血液中のヘモグロビンを増やすだけでは不十分です。私の専門分野では、心臓や血管、さらには糖尿病など基礎疾患との関連を意識した 包括的アプローチ を重視しています。ここでは種類別に治療法を整理し、実際の臨床でのポイントも詳しく解説します。
1. 鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血は最も一般的で、特に女性や高齢者に多く見られます。当院では単なる鉄補充ではなく、原因の解明と併行しての治療 を行います。
-
• 内服治療
硫酸鉄やフェロミア(フェリック鉄製剤)を用い、毎日あるいは隔日投与で体内鉄を補充します。隔日投与は吸収効率を上げ、副作用(便秘や胃腸障害)を軽減する効果があります。 -
• 静注鉄
内服で効果が不十分な場合や消化器障害で内服困難な場合に選択。点滴により短期間で鉄を補充可能です。 -
• 原因の同時治療
消化管出血や月経過多などの原因がある場合は、まずその治療を行うことが根本的な改善につながります。
鉄欠乏性貧血は放置すると、酸素供給不足から心拍数の増加や心不全リスク増加につながるため、早期対応が重要になってきます。
2. 腎性貧血
慢性腎臓病や糖尿病性腎症では、腎臓から分泌される造血ホルモン「エリスロポエチン」が不足します。この場合、単なる鉄補充では不十分です。
-
• エリスロポエチン製剤(ESA)
皮下注射や点滴でエリスロポエチンを補充。定期的にヘモグロビン値をモニタリングし、過剰投与を避けながら目標値に調整します。 -
• 鉄補充の併用
ESA単独では赤血球を作るための材料が不足することが多いため、静注鉄や内服鉄を併用することが多いです。
腎性貧血は心臓に大きな負荷をかけるため、循環器の視点を持つ当院では特に心不全リスクの低減を意識して治療しています。
3. 巨赤芽球性貧血(ビタミンB12・葉酸欠乏)
栄養障害や吸収不良による赤血球の成熟障害が原因です。
-
• ビタミンB12注射
筋注により速やかに赤血球を増加。特に神経症状(手足のしびれや感覚障害)がある場合は必須です。 -
• 葉酸内服
栄養補給として短期間で効果が出ます。アルコール多飲者や妊婦にも注意深く投与します。
巨赤芽球性貧血は血球が大きく脆いため、軽度でも心拍数増加や息切れの原因になります。
4. 溶血性貧血
赤血球が破壊されやすいタイプで、自己免疫性や遺伝性があります。
-
• 免疫抑制薬やステロイド
自己免疫性の場合に赤血球破壊を抑制。 -
• 遺伝性溶血
栄養管理や感染予防が中心で、必要に応じて赤血球輸血も行います。
溶血性貧血は急激にヘモグロビンが低下するため、心臓にかかる負荷が短期間で増加します。当院では早期診断と適切な輸血管理を徹底しています。
5. 骨髄疾患による貧血
再生不良性貧血など、造血機能そのものに問題がある場合は、治療法も高度化します。
-
• 造血幹細胞移植
若年者や重症例に対し、根治を目指した治療。 -
• 支持療法
輸血や感染予防を組み合わせ、体力を保ちながら病状管理します。
6. 輸血療法
急性貧血や手術前後のヘモグロビン低下には、短期的に酸素運搬能力を補う目的で輸血が行われます。ただし長期的には鉄過剰や免疫反応のリスクもあるため、必要最小限にとどめることが重要です。当院では輸血設備はないため、即座に日本医科大学付属病院や永寿総合病院などの高次機能病院に紹介いたします。
7. 治療における当院の特徴
私たちは単に数値を上げるだけでなく、心臓や糖代謝への影響を考慮しながら治療方針を決定します。
- • 狭心症患者や心不全患者では、軽度の貧血でも早期に鉄補充やESAを検討。
- • 糖尿病患者ではHbA1cの評価に貧血影響を加味し、過剰な薬物調整を避けます。
- • 定期的に血液検査と臨床症状をチェックし、必要に応じて栄養指導や生活改善も並行。
こうした包括的アプローチにより、単に血液の数字を改善するだけでなく、全身の酸素供給や心臓負荷を軽減し、日常生活のQOL向上も目指しています。
ここがポイント
「貧血くらい」と思わず、倦怠感や息切れ、動悸などを感じたら早めの検査をおすすめします。当院では循環器・糖尿病の両面から貧血の影響を評価し、個々の生活や基礎疾患に合わせた最適な治療を提供します。放置せず、早期に対策を行うことが心臓や全身の健康を守る第一歩です。
Hb濃度が低めで安定していると、体が悪い意味で低い血液濃度に慣れてしまい、症状が乏しい方が多いです。しかしながら適切に診断・治療を行いHb濃度を適正にすることで「すごく最近体調がよい。」「多少の無理な仕事も全然できるようになった。」などのお声をいただきます。
いつでもご相談いただければと思います。
- • Weiss G, et al. Anemia of chronic disease. N Engl J Med. 2005.
- • KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2012.
- • Ponikowski P, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016.
- • 日本循環器学会:心不全治療ガイドライン 2021.
- • 日本糖尿病学会:糖尿病診療ガイドライン 2023.