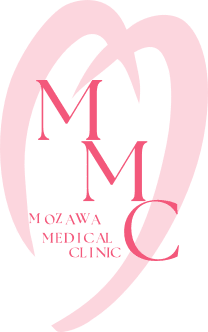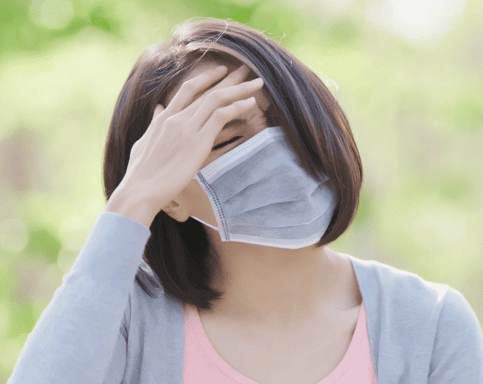頭痛は非常に一般的な症状で、誰もが一度は経験します。しかし、原因によっては命に関わる場合もあるため早期の診断や治療が重要です。
私の専門分野では、循環器疾患や代謝異常が背景にある場合の頭痛パターンも意識して診療に当たっています。
以下、頻度として高い頭痛から典型的な症状などをわかりやすくまとめて解説いたします。

茂澤 幸右
緊張型頭痛
(Tension-Type Headache; TTH)疫学
最も頻度が高く、成人の 30〜78%が生涯に一度は経験すると言われています。女性にやや多く、ストレスや長時間のデスクワーク、姿勢不良が誘因となります。
症状
- • 頭全体が締め付けられるような圧迫感
- • 首や肩の筋緊張を伴うことが多い
- • 吐き気や光過敏は比較的少ない
診断のポイント
- • 定期的で慢性化しても発作中は軽度であることが多い
- • 発作は数時間から数日続く
- • 神経学的異常や意識障害は伴わない
治療
- • 生活習慣改善:姿勢の矯正、睡眠リズムの安定、ストレスマネジメント
- • 薬物療法:鎮痛薬(アセトアミノフェン、NSAIDs)が第一選択
- • 頻度が多い場合は筋弛緩薬や抗うつ薬(低用量アミトリプチリン)を使用することもある
片頭痛
(Migraine)疫学
成人女性に多く、成人の 10〜15%が片頭痛を経験します。家族歴を伴うことが多い遺伝性要素があります。
症状
- • ズキンズキンと側頭部(こめかみあたり)に脈を打つような頭痛
- • 片側性が多い
- • 光過敏、音過敏、吐き気・嘔吐を伴うことがある(暗い静かな部屋にこもってしまうくらい症状が強く出る方もいます)
- • 前兆(閃輝暗点や視覚障害)がある場合も
診断のポイント
- • 発作は4〜72時間ほど続く
- • 日常生活が困難になるほど強い場合がある
- • 発作の頻度、誘因(ストレス、月経、食事)を詳しく聞くことが重要
治療
- • 急性期:トリプタン製剤(スマトリプタンなど)やNSAIDs
- • 予防的治療:β遮断薬、抗てんかん薬(バルプロ酸)、カルシウム拮抗薬、最近はCGRP抗体製剤も有効
- • 生活習慣の管理も必須(睡眠、カフェイン、ストレス管理)
循環器疾患のある方にはトリプタン使用に注意が必要です。狭心症や心筋梗塞の既往がある場合は原則避けるか、低リスク薬を選択します。
そのため薬物治療を始める前にかならず患者さんごとに既往歴や併存疾患を確認することを心掛けています。
群発頭痛
(Cluster Headache)疫学
男性に多く、人口の0.1%程度。典型的には季節性・周期性に発作が起こります。
症状
- • 目の周囲の強烈な痛み(片側)
- • 涙目、鼻閉、鼻水、眼瞼下垂など自律神経症状を伴う
- • 発作は15分〜3時間で繰り返す
診断のポイント
- • 一日に複数回、同時期に集中して発作が起こる
- • 痛みは非常に激烈で、座ってじっとしていられないこともある
治療
- • 急性期:酸素吸入、高用量トリプタン皮下注射
- • 予防的治療:カルシウム拮抗薬(ベラパミル)、ステロイド短期投与
群発頭痛は発作中の強烈な痛みが特徴で、救急受診される方も少なくありません。
見落としてはいけない頭痛
頭痛には上記に示した一次性頭痛(緊張型・片頭痛・群発頭痛)のほかに、二次性頭痛があり、特に以下の疾患は早急な対応が必要です。
くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage; SAH)
- • 特徴:「今まで経験したことのない激しい頭痛」「バットで殴られたような痛み」、嘔吐、意識障害、項部硬直を伴うことが多い
- • 診断:CT、腰椎穿刺
- • 治療:血管内治療(コイル塞栓術)や外科的クリッピング
放置すると生命に直結するため、発症から早急に搬送が必要です。
頭痛を訴える患者さんを目の前にして内科医としては一番意識し、除外をしなければならない最も怖い病態です。
発症すると約1/3の方は命を失い、1/3の方は命こそ助かるものの重い後遺症のため介護状態を要する、そして残り1/3の方は社会復帰ができるというデータがあります。
硬くスペースが限られている頭蓋内に出血してしまうことで、脳を血液や血腫が圧迫し多様な神経症状をもたらします。
原因には外傷性を除くと、主に脳動脈瘤とモヤモヤ病の2つがあります。
脳動脈瘤はうまれもった脳の血管のコブであり、普通の血管に比べて壁が脆弱で破れやすいです。
モヤモヤ病は比較的若年者に多く、細いもやもやした血管を持っていることで出血がしやすいです。
どちらも健康な時に脳ドック(MRI/MRA検査)を受けることで確認ができるため、予防医学の側面からも一度は検査を受けることを強くお勧めします。
脳腫瘍
- • 徐々に増悪する頭痛、吐き気、視覚障害、言語障害、片麻痺など
- • MRIやCTで診断
- • 手術・放射線・化学療法が治療選択
高血圧性頭痛・脳血管障害
- • 高血圧性危機(BP 180/120 mmHg以上)では頭痛、視覚障害、意識障害
- • 急性期は降圧管理と臓器保護が重要
循環器・代謝視点での頭痛管理
- • 高血圧や心疾患、糖尿病患者では、頭痛が 心血管リスクのサイン であることがあります。
- • 片頭痛患者では、心筋梗塞や脳梗塞のリスク増加が報告されています(特に女性・喫煙者)。
- • 循環器疾患リスクがある方にトリプタンを投与する場合は、必ず心電図や既往歴を確認します。
治療の基本方針
一次性頭痛の治療
- • 鎮痛薬、トリプタン製剤など
- • 生活習慣改善(睡眠、ストレス管理)
- • 予防薬(β遮断薬、カルシウム拮抗薬、抗てんかん薬、CGRP抗体)
二次性頭痛の鑑別
- • 突発・劇烈・増悪型の頭痛は必ず画像検査
- • 脳出血、脳腫瘍、感染症の可能性を除外
日常生活の工夫
- • 姿勢、眼精疲労対策
- • 水分・食事・睡眠リズムの管理
- • 循環器・代謝疾患の管理が頭痛悪化の予防に寄与
当院の診療方針
私たちは頭痛を単なる「痛み」としてではなく 全身の健康状態のサインとして捉えています。
- • 初診時には問診・身体診察に加え、必要に応じてMRIやCTを迅速に実施できる医療機関に紹介いたします
- • 循環器疾患・糖尿病などの基礎疾患の影響を評価
- • 患者さんの生活背景に沿った薬物治療と生活習慣改善を組み合わせ、再発予防まで包括的にサポート
頭痛は放置すると生活の質を大きく損なうだけでなく、重篤な疾患の兆候であることもあります。早期に適切な診断と治療を行うことが最も重要です。
- • Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018.
- • Goadsby PJ, et al. Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol Rev. 2017.
- • May A, et al. Cluster headache: pathophysiology and management. Lancet Neurol. 2005.
- • Connolly ES, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2012.
- • 日本頭痛学会:頭痛診療ガイドライン 2021