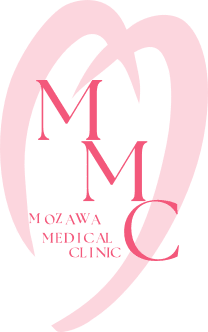糖尿病の本当に恐ろしい側面はこれから説明する各臓器障害といっても過言では有りません。これから解説する腎臓・網膜(眼)・神経・心臓への悪影響は背景に共通する病態があります。それは微細な血管や神経が長い間、高血糖にさらされることで損傷(ボロボロ)し、最終的には機能が低下していくということです。
上記の臓器は全て毛細血管・神経がとても豊富であるという点も一致します。
糖尿病性腎症(糖尿病の三大合併症)
糖尿病は「血糖値が高いだけの病気」ではなく、長い間放置するとさまざまな合併症を引き起こすことが大きな問題です。その中でも「糖尿病性腎症」は、進行すると人工透析が必要になる可能性のある深刻な合併症のひとつです*¹。腎臓は替えの利かない大切な臓器であり、科学技術が進歩した現在でも廃絶した腎臓を再生することは困難です。そのため腎臓が機能しなくなった方は体外で腎臓の機能をもつ人工血液透析にたよらざるを得なくなるのです。
-
腎臓の働きとは?
腎臓は体のフィルターのような役割をしており、血液の中から不要な老廃物を尿として内外へ取り除き、血液をキレイにしてくれる重要な臓器です。
-
イメージ:
汚れた水をキレイにろ過するフィルターが詰まってしまうと、うまく水を浄化できなくなり濁ったり汚染されていきますよね?それと同じように、フィルター(腎臓の糸球体という部分)がダメージを受けると体の老廃物をうまく排出できなくなります。
糖尿病性腎症の原因
糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、腎臓の細かい血管(糸球体)がダメージを受けることで、腎臓の働きが低下してしまいます*²。 特に高血糖だけでなく、高血圧や高コレステロールも関係しており、腎臓への負担がさらに増えてしまいます。 先述の通り腎臓は体のろ過装置のため微細な毛細血管がとても豊富にはりめぐらされています。血管にダメージを与える過度な糖や血圧などに長期にさらされるとボロボロに傷んでしまい、しいては機能不全にいたってしまうのです。
糖尿病性腎症の進行と症状
糖尿病性腎症は自覚症状がほとんどないまま進行していきます。
-
・第1〜2期(初期段階)
ほとんど自覚症状なく、たんぱく質(アルブミン)が尿に少しずつ漏れ始める。
→ この段階で生活習慣の改善をすれば、進行を食い止めることができます。 -
・第3期(中等度)
尿にたんぱくが多く漏れる(たんぱく尿)状態で足先にはむくみが出始めることもあります。
-
・第4〜5期(重症)
腎臓の働きが大きく低下し、体の老廃物が正常に排出できなくなる状態をさします。 「透析療法(人工透析)」が必要になる可能性が高まり、ここまで進むと元に戻すことが難しくなります。
糖尿病性腎症を防ぐためにできること
糖尿病性腎症は早い段階で発見し、適切な管理を行えば進行を止められる可能性があります。以下を当院では意識しております。
-
定期的な検査を受ける
- 尿検査・血液検査で早期発見
-
血糖値を適切に管理する
- ドカ食いによる急激な変動を防ぐ
-
血糖の他に血圧やコレステロール値も意識する
- 腎臓の負担を減らす
-
減塩を意識した食事を心がける
- 塩分の摂りすぎは腎臓に負担をかける
-
適度な有酸素運動をする
- 腎臓に流入する血液量が増加する
ここがポイント
当院では、糖尿病性腎症の早期発見と進行予防に力を入れています。「透析にならないようにするために、今できること」を一緒に考え、個別の治療プランを提案します。 腎臓は一度ダメージを受けると回復が難しい臓器ですが、正しい管理をすれば健康な状態を保つことができます。気になることがあれば、遠慮なくご相談ください。
- *¹ American Diabetes Association. "Diabetic Nephropathy: Pathophysiology and Therapeutic Targets." Diabetes Care. 2017.
- *² Tuttle KR, et al. "Diabetic Kidney Disease: A Report From the ADA Consensus Conference." Diabetes Care. 2014.
- *³ Wada T, et al. "Pathogenesis and Management of Diabetic Nephropathy in Japan." Kidney International. 2020.
糖尿病性網膜症
糖尿病が長く続くと目の奥にある「網膜」という部分の細かい血管がダメージを受け視力に影響を及ぼす「糖尿病性網膜症」を発症することがあります*¹。 進行すると失明の原因にもなり得るため、早期発見と適切な治療が重要です。
糖尿病性網膜症の原因と進行
網膜はカメラで例えるなら「フィルム」のような部分で、目に入った光を映し出す大切な組織です。しかし糖尿病によって血糖値が高い状態が続くと、網膜の細い血管が傷つき、血流が悪くなることで異常が起こります*²。
-
初期(単純網膜症):
自覚症状なし。網膜の血管が少し膨らんで点状出血が見られることがある。
-
中期(増殖前網膜症):
血管の詰まりが進み、視力が低下し始める。
-
重症(増殖網膜症):
網膜に新しい異常血管ができ、出血や網膜剥離が起こり失明のリスクが高まる。
★「視力が落ちたと感じたときには、すでに病状が進んでいることが多い」のが特徴です。
進行するとどんな症状が出る?
-
視力が低下する
- かすみ目、見えづらさ
-
暗いところでより物が見えにくい
- 夜間の視力低下
-
視界に黒い影や蚊が飛んでいるような点が現れる
- 飛蚊症
-
突然、視力が大きく低下する
- 硝子体出血
糖尿病性網膜症の予防と治療
糖尿病性網膜症は、血糖値の適切なコントロールが何よりも大切です。
-
血糖値を安定
- 血液検査でわかる血糖値の平均値であるHbA1cの管理
-
血圧・コレステロールをコントロールする
- 血管をストレスから保護する
-
定期的に眼科検診を受ける
- 年1回は眼科受診を!
★ 進行してしまった場合、レーザー治療や硝子体手術などの治療が必要になることもありますが、早期発見すれば進行を抑えることができます*³。
ここがポイント
当院では糖尿病患者さんに定期的な眼科検診を推奨し、専門医と連携した診療 を行っています。具体的には3か月~半年に1回は眼科で眼底検査や眼圧検査をうけてもらい網膜の状態を評価・治療してもらうように促しております。 また重度な糖尿病をもつ方が急に気合をいれて断食をしたりする方も時折いらったしゃいます。そうした急激な血糖の低下はかえって進行した網膜症には悪影響を及ぼしますので、地に足をつけた中長期的な管理の視点も重要になってきます。
- *¹ Cheung N, et al. "Diabetic Retinopathy." The Lancet. 2010.
- *² Antonetti DA, et al. "Diabetic Retinopathy: Seeing Beyond Glucose-Induced Microvascular Disease." Diabetes. 2006.
- *³ Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. "Early Photocoagulation for Diabetic Retinopathy." Ophthalmology. 1991.
糖尿病性神経障害
糖尿病が進行すると、神経がダメージを受ける「糖尿病性神経障害」を引き起こすことがあります。これは糖尿病の合併症の中で最も早い段階から現れることが多いとされています*¹。 手足のしびれや痛みだけでなく、自律神経を介して内臓の働きにも影響を与え、生活の質を大きく低下させることもあります。
糖尿病性神経障害の原因と進行
私たちの神経は体内では電気信号を伝える「配線」のような役割を担っています。しかし高血糖状態が続くと神経の細胞がダメージを受け、正常な働きができなくなります*²。 前項の腎臓や網膜(眼)の障害は微細な血管が傷つくことで機能が低下していきますが、今回は微細な神経が傷つくことで生じます。
どのように進行する?
-
初期: 手足の軽いしびれや違和感が出始める。ほとんど無症状が多い。
-
中期: 痛みや冷え、ほてりなどの異常感覚が強くなる。
-
重症: 感覚が鈍くなり、傷ややけどに気づかなくなる。
特に足の感覚が鈍くなると、気づかないうちに傷ができ、さらに状態が悪化し重症化すると「糖尿病性足壊疽(えそ)」につながることもあります。 壊疽は腐るという言葉の医療用語です。こうなってしまうと自力での傷口の治癒が困難なケースが多く最悪の場合は足を切断しなければならなくなることがあります。 そのまま腐り続ける足を放置し続けると、繁殖した細菌(いわゆるばい菌)が血中から全身に回り(菌血症、敗血症などと医療現場では用います)、死をもたらすことがあるからです。
どんな症状が出るの?
糖尿病性神経障害は影響を受ける神経の種類によって症状が異なります。
-
感覚神経の障害: 手足のしびれ・痛み・冷え
-
自律神経の障害: 立ちくらみ、胃もたれ、便秘・下痢
-
運動神経の障害: 筋力の低下、歩きにくさ
★ 特に「足のしびれや違和感」は初期のサインとして出やすいので、放置せず早めに対策をとることが大切です。
糖尿病性神経障害の予防と治療
糖尿病性神経障害は早期発見と血糖管理が最も重要です。
-
血糖値の適切なコントロール
- HbA1cを目標範囲に維持
-
足のセルフチェック
- 傷や火傷跡などの異常がないか確認する
-
ビタミンB12や葉酸などの栄養管理
- 末梢神経の健康維持
-
適度な有酸素運動と微弱なマッサージ
- 血流を促進
すでに神経障害が進行している場合は、痛みを抑える薬(プレガバリン・デュロキセチン)や血流を改善する治療が必要になることもあります*³。
ここがポイント
糖尿病性神経障害は「ただのしびれ」と思っているうちに進行する怖い状態」です。しかし適切な血糖コントロールと日常的なケアを続ければ、症状の進行を防ぐことが可能 です。 当院では神経障害の早期発見のためのチェックを行い、患者さんに合わせた適切な生活指導や治療を提供しています。「最近手足がしびれる」「足が冷たいのに温かく感じる」そんな違和感がある方は、お気軽にご相談ください。本項冒頭でも述べた通り、糖尿病初期に現れる大事なサインですので早めの認知と行動がカギになります。
- *¹ Tesfaye S, et al. "Diabetic Neuropathy." The Lancet. 2010.
- *² Feldman EL, et al. "Diabetic Neuropathy." Nature Reviews Endocrinology. 2019.
- *³ Bril V, et al. "Evidence-Based Guideline: Treatment of Painful Diabetic Neuropathy." Neurology. 2011.