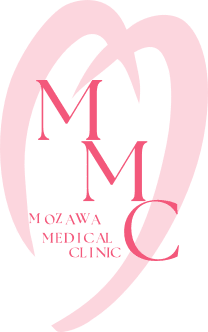高血圧とは?
通高血圧はその名の通り血圧が通常よりも高くなり、心臓や血管に負担をかけてしまう症状です。 多くの場合はっきりとした原因はわからず、本人が気づかぬうちに心臓や血管にダメージを与えていって合併症を引き起こしてしまいます。 その性質のため「サイレントキラー」と呼ばれています。
高血圧の診断には家庭血圧と診察室血圧の両方を評価することが推奨されています。 日本高血圧学会のガイドラインでは診察室血圧が140/90 mmHg以上、または家庭血圧が135/85 mmHg以上で高血圧と診断されます。 特に白衣高血圧(診察室だけ異常に高い)や仮面高血圧(診察室では正常でも家庭で高い)といったタイプもあるため、家庭での定期的な血圧測定が重要です*¹。
- 高血圧は以下の2種類に大きく分類されます。
・本態性高血圧(約90%):明確な原因がなく、遺伝や加齢、生活習慣が関与する
・二次性高血圧(約10%):腎臓疾患やホルモン異常など特定の原因がある
- *¹: 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2022」
高血圧の症状
はっきりとした自覚症状がない高血圧症ですが、以下の症状がある場合、高血圧を疑います。
ご自分が高血圧かどうかを把握するためには自分の血圧を常日頃把握しておくことが大事になってきます。
血圧の標準値(基準値)は、日本高血圧学会が2004年に定めた血圧の判定基準によると、成人の場合最高血圧140mmHgまたは最低血圧90mmHg以上を高血圧としています。
もしご自分が高血圧かと思われる場合は他の合併症も疑われるため、一度ご相談下さい。
こんな症状ありませんか?
-
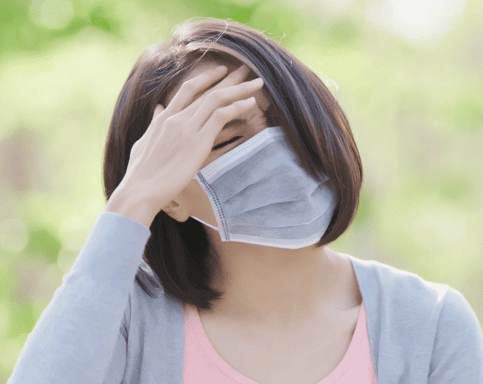
頭痛がする
-
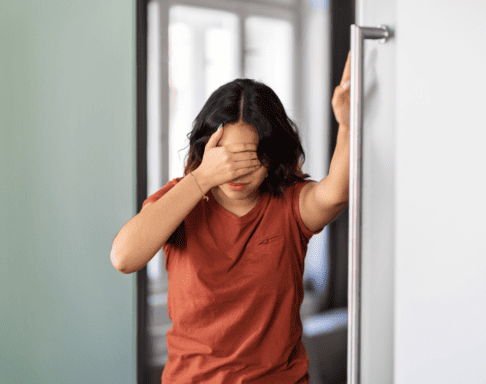
めまいがする
-

耳鳴りがする
-

動悸がある
-
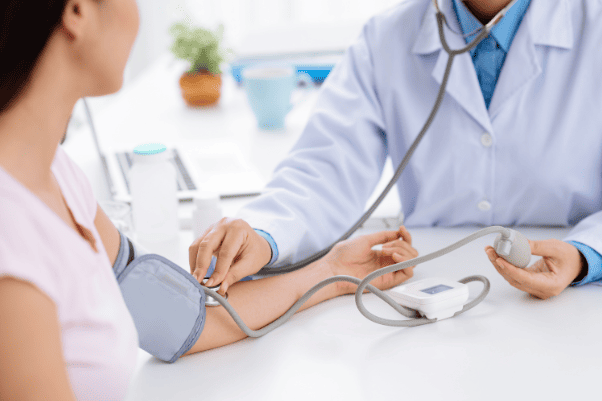
血圧が高い
併発する症例

動脈硬化、心臓病、脳梗塞、脳出血、など
高血圧の原因
高血圧の主な要因には以下のようなものがあります。
-
▶︎ 生活習慣
塩分摂取過多、運動不足、肥満、喫煙、過度の飲酒
-
▶︎ ストレス・自律神経の影響
交感神経の過剰な働き
-
▶︎ 加齢
血管の弾力低下≒血管のしなやかさが失われ硬くなっていく
-
▶︎ 遺伝的要因
家族歴
特に塩分の過剰摂取はナトリウムが体内に水分を溜め込み、血液量を増やして血圧を上げる要因となります。日本人の食塩摂取量は世界的に見ても多く、減塩は重要な対策の一つです*²。
- *²: WHO「塩分摂取と健康リスク」
高血圧の検査・診断
-
- 血液検査
腎機能(クレアチニン、eGFR)、電解質(特にナトリウム・カリウム)、血糖、脂質プロファイル
-
- 尿検査
尿蛋白、アルブミン/クレアチニン比(早期腎障害の評価)
-
- 心電図
左室肥大や不整脈の評価
-
- 心エコー
心筋肥厚、左室拡張機能、弁膜症の有無をチェック
-
- 眼底検査
高血圧性網膜症の確認(重症高血圧では必須)
また、二次性高血圧(腎血管性高血圧、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫など)が疑われる場合は、ホルモン検査やCT/MRIなどの精密検査を追加します。 後ほど述べる薬物治療を開始し、複数の薬剤を組み合わせてもなかなか血圧コントロールが難しい方は二次性高血圧が背景にあることがあります。
高血圧治療の基本戦略
高血圧治療の基本は2本柱「生活習慣の改善」と「薬物治療」の両立です。軽症であれば有酸素運動のルーチン確立や減塩などの生活習慣の改善だけで管理できることもありますが、多くの場合は薬物療法が必要です。
降圧薬の種類と特徴
1. Ca拮抗薬(CCB:カルシウムチャネルブロッカー)
- ⚫︎ 例:アムロジピン、ニフェジピンCRなど
- ⚫︎ 血管平滑筋に作用し、血管を拡張することで血圧を下げます。
- ⚫︎ 高齢者や脳血管障害の既往がある方に有効。
- ⚫︎ 副作用:下肢浮腫、動悸、顔のほてり
一昔前はこの薬が降圧薬の柱となっておりましたが、現在は下記の最新薬剤にその座を譲っています。頻脈や頭痛、足のむくみ、歯肉腫脹などの副作用に留意しながら私も時折使用しております。 心不全の方には使用しづらく、持病のない比較的若い方に処方する機会が多いです。
2. ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)/ACE阻害薬
-
⚫︎ 例(ARB):テルミサルタン、バルサルタン
例(ACE):エナラプリル、イミダプリル - ⚫︎ 心血管イベントや腎保護効果があるため、糖尿病・心不全・腎障害を併せ持った方に有用。
- ⚫︎ 副作用:高カリウム血症、空咳(ACE阻害薬)
心臓や腎臓の保護効果が大規模研究で発見され、歴史もある薬剤です。 ACE阻害薬は主に心不全の薬として用いられますが、ARBは高血圧の治療薬としては第一手として選択することが多いです。 副作用にナトリウムやカリウムといった電解質(体内のミネラルバランス)が崩れることもあるため処方後は血液検査での評価も大切になります。
3. 利尿薬
- ⚫︎ 例:ヒドロクロロチアジド、トリクロルメチアジド、フロセミド
- ⚫︎ ナトリウム排泄を促進し、血液量を減少させて血圧を下げます。
- ⚫︎ 高齢者や塩分感受性の高い人に有効。心不全の補助薬としても。
- ⚫︎ 副作用:電解質異常(低K血症など)
高血圧が主体の心不全になったことがある方に補助的に用いる薬です。 特に塩分過多の方には著効するケースもあります。 脱水になると腎臓機能が低下することもあるため、定期的に血液検査も必要になります。
4. β遮断薬
- ⚫︎ 例:ビソプロロール、カルベジロール
- ⚫︎ 心拍数と心拍出量を抑えて降圧効果を示します。
- ⚫︎ 心疾患(狭心症、不整脈、心不全)の合併がある場合に有効。
- ⚫︎ 副作用:徐脈、疲労感、勃起障害など
この薬剤は抗心不全薬として長年君臨しています。
循環器専門医は使い慣れており、特に普段の脈拍が高めの方(脈拍が1分間に80回以上など)には心保護の観点からも理にかなっています。
個人的にはARBやARNiを内服しても効果不十分の場合に追加で処方することが多いです。
その一方で導入時や用量によっては、低血圧や徐脈を引き起こし倦怠感やめまいなどを引き起こすこともあるため慎重な管理が必要です。
5. MR拮抗薬(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)
- ⚫︎ 例:エプレレノン、エサキセレノン
- ⚫︎ 特に原発性アルドステロン症や難治性高血圧に有用。
- ⚫︎ 心不全合併例での予後改善効果も注目。
- ⚫︎ 副作用:高カリウム血症、女性化乳房
6. ARNI(エンレスト/サクビトリル・バルサルタン)
- ⚫︎ 従来のARBにネプリライシン阻害薬(サクビトリル)を組み合わせた新しい薬剤。
- ⚫︎ 「心不全」において非常に有用であり、近年高血圧も保険診療適用となったことで最も注目されている薬剤。
朝1回で強い降圧効果も有するが、低血圧や電解質異常など取り扱いも難しいため専門家での管理が望ましい薬剤です。
生活習慣の見直しも重要
上記の薬に加えて、以下のような生活習慣の改善が血圧コントロールには不可欠です
-
- 減塩(1日6g未満が目標)
-
- 適度な運動(有酸素運動を週に150分程度、定期的に行うことが大切)
具体的にはウォーキング、水中ワーキング、自転車漕ぎ、軽いジョギングなど -
- 節酒、禁煙
-
- ストレス管理、十分な睡眠
-
- 体重管理
肥満であること自体が高血圧の原因となるため、BMI 22を目標とした適正な体重維持も重要。体重を適正化することでもともと内服していた降圧薬を減量・中止なども可能になるケースが多いです。
- *日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2023
- *McDonagh TA et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.
- *Yusuf S, et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993-1004.