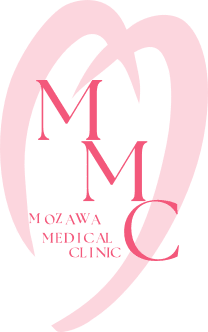肝機能障害とは?
健康診断の結果に「AST(GOT)」「ALT(GPT)」「γ-GTP」が⾼い、と指摘されたことはありませんか? これらは肝臓の状態を⽰す⾎液検査の代表的な項⽬です。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、障害が進んでも⾃覚症状が出にくい最⼤の臓器です。 そのため健診の数値は、症状が出る前の重要なサインになります。 例えるなら、肝臓は「24 時間稼働の⼯場」です。⼯場内の機械(肝細胞)が傷つくと、その部品(酵素)が⾎液中に漏れ出します。これが AST や ALT の上昇です。
健診で指摘されることの多い項⽬と意味
| 項⽬ | 主な意味 |
|---|---|
| AST(GOT) | 肝臓・⼼臓・筋⾁の障害で上昇。肝障害だけでなく筋⾁疾患でも変化。 |
| ALT(GPT) | 肝臓特異性が⾼く、ALT ⾼値は肝細胞障害を強く⽰唆。 |
| γ-GTP | 主に胆汁うっ滞やアルコール性障害で上昇。飲酒習慣の指標にも。 |
| ALP | 胆道系の障害で上昇しやすい。 |
| ビリルビン | ⻩疸の指標。慢性肝疾患や溶⾎でも変化。 |
- ⽇本肝臓学会「肝機能異常の診断と治療指針」(2022 年版)
主な原因
1. 脂肪肝(NAFLD/NASH)
- ・肝細胞に脂肪が蓄積。過⾷・肥満・糖尿病・脂質異常症が背景。
- ・「アルコールを飲まないのに肝障害」というケースも多い。進⾏すると⾮アルコール性脂肪肝炎(NASH)になり、肝硬変・肝癌リスクが上昇。
2. アルコール性肝障害
- ・⻑期の飲酒により脂肪肝→アルコール性肝炎→肝硬変へ進⾏。
- ・γ-GTP ⾼値が特徴。
3. ウイルス性肝炎(B 型・C 型)
- ・感染により慢性的な炎症を起こし、数⼗年単位で肝硬変・肝細胞癌のリスク上昇。
- ・C 型は現在ほぼ 100%近く経⼝薬で治癒可能。
4. ⾃⼰免疫性肝炎・原発性胆汁性胆管炎(PBC)
- ・⾃⼰免疫反応で肝臓や胆管が障害される。⼥性に多い。
- EASL Clinical Practice Guidelines: Management of liver diseases(2023)
放置した場合の進⾏リスク
肝障害を無治療で経過すると、次の流れで進⾏します:
脂肪肝・慢性炎症 → 線維化 → 肝硬変 → 肝細胞癌
これはまるで「サビがついた鉄」が放置されて腐⾷し、最後には⽳があくようなもの。肝臓も修復と破壊を繰り返すうちに組織が硬くなっていきます。
上記の流れの中で線維化まで⾄ってしまうと、もう正常な肝細胞には戻れないのも重要なポイントです。
- ⽇本肝癌研究会「肝細胞癌取扱い規約(2021 年版)」
診断⽅法
1. ⾎液検査
AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビン、HBs 抗原、HCV 抗体など。
2. 腹部超⾳波(エコー)
脂肪肝では「明るく映る」像。肝硬変では凹凸のある表⾯や脾腫、腹⽔を確認できます。肝細胞癌を疑うような腫瘍像も指摘できることがあります。
3. CT/MRI
詳細な脂肪量、腫瘍の有無の評価。
- AASLD Practice Guidance on the Clinical Assessment and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease(2023)
治療⽅法
1. 原因除去
- ・アルコール性 → 断酒
- ・脂肪肝 → 減量(体重 5〜10%減)
- ・ウイルス性肝炎 → 抗ウイルス薬
2. ⽣活習慣改善(脂肪肝・軽度異常で特に重要)
- ・栄養:糖質・脂質の過剰摂取制限。地中海⾷パターンが推奨。
- ・運動:有酸素運動+筋トレを週 150 分以上。
- ・睡眠とストレス管理。
3. 薬物療法
- ・NASH → ⼀部で糖尿病薬(GLP-1 受容体作動薬)が有効との報告あり。
- ・⾃⼰免疫性肝炎 → ステロイド+免疫抑制薬。
- ⽇本消化器病学会「NAFLD/NASH 診療ガイドライン(2022 年)」
ここがポイント
B・C 型肝炎が最近では圧倒的に少なくなり、肝機能障害の⼤半はアルコール性と脂肪肝による原因です。この 2 つの原因のどちらか 1 つが原因というよりは両者ともに原因で抜本的な⽣活改善が必要になることが多いです。 まずは現状の体重や⾷事内容、総カロリー、アルコールの頻度や総量などを把握し、⾃分の肝臓と向き合うことが⾮常に重要です。 その健康管理をサポートできるように私も精進していきたいと思います。
腎機能障害とは?
健康診断や⼈間ドックの結果で「クレアチニン(Cr)」「eGFR」「尿たんぱく」が⾼い/低い、と指摘された経験はありませんか?
腎臓は背中側、腰のやや上に左右 1 つずつある握りこぶし⼤の臓器で、⾎液をろ過し⽼廃物や余分な⽔分を尿として排出します。さらに⾎圧調整やホルモン分泌にも関与する、いわば⾼性能な⽔処理プラント+化学⼯場です。
しかし腎臓も「沈黙の臓器」のひとつで、障害が進⾏しても初期は症状が出にくいのが特徴です。そのため健診の数値は早期発⾒のための重要なサインとなります。
健診でよく指摘される項⽬と意味
| 項⽬ | 主な意味 |
|---|---|
| クレアチニン(Cr) | 筋⾁の代謝産物。腎機能低下で⾎中に蓄積。 |
| eGFR(推算⽷球体濾過量) | 腎臓が 1 分間にどれだけ⾎液をろ過できるかを推定した値。60 未満で要注意。 |
| 尿たんぱく | ⽷球体や尿細管の障害で漏れ出す。慢性腎臓病(CKD)の早期サイン。 |
| 尿潜⾎ | 尿路結⽯、腎炎、腫瘍など多様な原因で出現。 |
| ⾎尿酸値 | ⾼値は腎障害や痛⾵のリスク。 |
- ⽇本腎臓学会「CKD 診療ガイドライン 2023」
主な原因
1. ⽣活習慣病由来(糖尿病性腎症・⾼⾎圧性腎硬化症)
- ・糖尿病や⾼⾎圧により腎臓の細い⾎管が傷つき、⻑期的にろ過機能が低下。
- ・⽇本の透析導⼊原因の第 1・2 位。
2. 慢性⽷球体腎炎
- ・⾃⼰免疫や感染後の免疫反応により⽷球体が炎症を起こす。
- ・若年〜中年での発症も多い。
3. 多発性嚢胞腎(遺伝性)
- ・腎臓に多数の嚢胞ができ、徐々に正常組織を物理的に圧迫し機能障害をきたす。
4. 薬剤性腎障害
- ・⼀部の鎮痛薬(例えばロキソニンなどの NSAIDs や抗菌薬、ステロイドなど)、検査に⽤いる造影剤、抗がん薬などが原因。サプリや健康⾷品などでも当然腎障害は起こりうるため最近はニュースになり注⽬されています。
5. 急性腎障害(AKI)
- ・脱⽔、敗⾎症、外傷、⼤出⾎などで急激に体の中の⽔分量が枯渇してしまい腎機能が悪化することがあります。
- KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD(2022)
放置した場合の進⾏リスク
腎障害は次のステップを経て進⾏します:
軽度腎機能低下 → 慢性腎臓病(CKD) → 腎不全 → 透析または腎移植
これは川の上流で起きた汚染が、下流の浄⽔施設に負担をかけ続け、ついに機能停⽌するようなものです。
腎機能は⼀度⼤きく失われると回復が難しいため、早期の対応が重要です。
- ⽇本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況(2023 年)」
診断⽅法
1. ⾎液検査
クレアチニン、eGFR、BUN(尿素窒素)、電解質(Na、Kなど)。
2. 尿検査
尿たんぱく、尿潜⾎、尿沈渣。
3. 画像検査
- - 腹部エコー:腎の⼤きさ、構造、結⽯の有無。
- - CT/MRI:腫瘍や⾎流評価。
4. 腎⽣検
原因精査のため腎臓組織を顕微鏡で観察。
治療⽅法
1. 原因除去
- 糖尿病性腎症 → ⾎糖の適性なコントロール(HbA1c 7%未満を⽬標)
- ⾼⾎圧性腎障害 → 腎保護効果を有する降圧薬の適切な使⽤ (ACE阻害薬やARB、最近ではARNiも注⽬されています。)
- 薬剤性 → 原因薬や物質の中⽌
2. ⽣活習慣改善
- ⾷塩制限:1 ⽇ 6g 未満(過剰な塩分は⾎圧と腎臓への負担を増加)
- タンパク質制限:中等度 CKD では 0.8g/kg 体重/⽇程度
- ⽔分バランス:脱⽔と過剰摂取の両⽅を避ける
- 禁煙:喫煙は腎⾎流を低下させる
3. 薬物療法
- レニン-アンジオテンシン系抑制薬(ACE 阻害薬・ARB)
- フィネレノン:腎保護効果が実証され注⽬されている新薬。
⾮ステロイド性ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(ns-MRA)で、2022年に⽇本で承認された⽐較的新しい腎保護薬です。
主に2型糖尿病を合併した慢性腎臓病(CKD)患者に使われます。
特徴
- ・従来のスピロノラクトンやエプレレノンより⾼カリウム⾎症のリスクが低い
- ・⽷球体や腎間質の炎症・線維化を抑える作⽤
- ・⼼⾎管イベントの抑制効果も報告
主なエビデンス
-
- FIDELIO-DKD 試験(NEJM 2020)
フィネレノンはプラセボに⽐べ、腎イベント(腎機能悪化や透析導⼊)を 18%減少、⼼⾎管イベントを 14%減少。 -
- FIGARO-DKD 試験(NEJM 2021)
主に⼼⾎管アウトカム改善を確認。
注意点
- ・高カリウム血症のリスクはゼロではないため、開始後は血清K値の定期チェックが必要
- ・RAS阻害薬と併用されることが多い
- Bakris GL et al. N Engl J Med 2020;383:2219-2229.(FIDELIO-DKD)
- Pitt B et al. N Engl J Med 2021;385:2252-2263.(FIGARO-DKD)
-
SGLT2 阻害薬:糖尿病性腎症・⾮糖尿病性 CKD にも有効性が数多く報告されており、現在の治療の中⼼となる薬。
(※糖尿病のコラムでも詳しく解説しております。) -
利尿薬:浮腫・⾼⾎圧コントロール
⽇本腎臓学会「CKD 診療ガイドライン 2023」
ここがポイント
年齢を重ねると当然腎機能も緩やかに低下していきます。 ここまで医療技術が発展した現在でも多くの透析を受けなければいけない方がいます。その事実は‘腎臓は替えの利かない臓器’であるということの裏返しです。 透析でしていることは、腎臓が本来は行ってくれている血液のろ過や体液量の調整を体外で大きな機械を作って代替しているにすぎません。 現在は上記でも記述したように腎臓を保護する薬剤が複数開発され注目されています。これらを正しく使用することも重要ですが、まずは自身の腎機能を把握してフォローしていくことが最初の1歩になると思います。