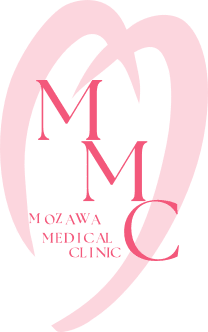甲状腺とは?
甲状腺はわずか20g前後の小さな臓器ですが、全身代謝の「司令塔」として機能し、心血管系・代謝系・神経系に広範な影響を及ぼします。臨床現場では、倦怠感や動悸、不整脈、浮腫、体重変化といった症状の背景に甲状腺機能異常が潜んでいることは珍しくありません。
特にバセドウ病による甲状腺機能亢進症は、心房細動(AF)や心不全を誘発する主要なリスク因子であり、循環器内科領域と極めて密接な関係を有しています。また橋本病を代表とする機能低下症は脂質異常症(高脂血症、高コレステロール血症)やインスリン抵抗性を増悪させ、糖尿病や動脈硬化性疾患の進展に影響を与えます。
内科医である私は、常に心疾患や代謝疾患のコントロールに難渋する症例において、甲状腺機能を必ず年頭におきながら総合的に診察することを心掛けています。

茂澤 幸右
甲状腺ホルモンの基礎と検査の読み方
甲状腺ホルモンはT4(サイロキシン)とT3(トリヨードサイロニン)が主体で、末梢でT4からT3に変換されて作用します。分泌は視床下部-下垂体-甲状腺(HPT軸)により制御され、**TSH(甲状腺刺激ホルモン)**がフィードバックの中心を担います。
臨床での基本的な解釈は以下の通りです:
- • TSH低値 + fT4高値:甲状腺機能亢進症(例:バセドウ病)
- • TSH高値 + fT4低値:甲状腺機能低下症(例:橋本病進行期)
- • TSH高値 + fT4正常:潜在性甲状腺機能低下症
- • TSH低値 + fT4正常:潜在性甲状腺機能亢進症
加えて、抗体検査の解釈も重要です:
- • TRAb(TSH受容体抗体):バセドウ病の診断・治療経過の評価
- • 抗TPO抗体、抗サイログロブリン抗体:橋本病の診断根拠
これらを組み合わせることで「機能異常の有無」と「自己免疫性か否か」を整理できます。
バセドウ病と心血管系への影響
(1) 病態
バセドウ病は自己抗体(TRAb)による甲状腺刺激でホルモンが過剰分泌される疾患です。典型的には動悸・手指振戦・体重減少・多汗などを呈しますが、最も臨床的に重要なのは心房細動の発症リスクです。
甲状腺ホルモン過剰はβ受容体を介して心筋興奮性を高め、洞性頻脈や心房期外収縮を誘発します。その結果、持続性のAFに移行しやすくなります。バセドウ病患者のAF発症率は一般人口の3〜5倍とされ、特に高齢者では心不全や脳塞栓症のリスク増加につながります。
そのため心不全のページでも詳しく述べておりますが、適切なβ遮断薬による脈拍コントロールが非常に重要です。
(2) 治療戦略
治療の第一歩は甲状腺ホルモンの是正です。抗不整脈薬や抗凝固療法を行っても、背景の甲状腺中毒症を改善しなければ根本的なリズムコントロールは困難です。
- • **抗甲状腺薬(メチマゾール第一選択)**で機能を安定化
- • 前述の通り動悸・頻脈に対しては**β遮断薬(プロプラノロール等)**を併用
- • AF持続例では場合により抗凝固薬を導入したり、電気ショックを考慮します
繰り返しになりますが内科医としては、「動悸=すぐに循環器的対応」ではなく、背後に甲状腺疾患がないかを疑う姿勢が不可欠です。
橋本病と代謝・循環器系への影響
橋本病は自己免疫性の慢性甲状腺炎で、進行すると機能低下症を呈します。症状は倦怠感・浮腫・体重増加・便秘・抑うつなど多彩ですが、生活習慣病との関連が臨床上重要です。
(1) 脂質異常症と動脈硬化
甲状腺ホルモンは肝臓でのLDL受容体発現を促進し、コレステロール代謝に関与します。機能低下症ではLDLコレステロールが上昇し、粥状動脈硬化が進展します。潜在性低下症でも心筋梗塞や脳卒中のリスク増加が示唆されており、内科診療で見逃すべきでない病態です。
(2) 糖代謝異常との関連について
甲状腺機能低下はインスリン抵抗性を高め、2型糖尿病の血糖コントロールを悪化させます。一方、機能亢進症では肝臓での糖新生促進により耐糖能異常を招きます。糖尿病患者における甲状腺疾患合併率は一般人口の2〜3倍とされ、双方向の関連が強い領域です。
(3) 循環器への影響
機能低下症では徐脈や心膜液貯留が見られることがあり、重度では粘液水腫性昏睡に至ることもあります。虚血性心疾患を合併する患者では、補充療法を急ぎすぎると狭心症や心不全を誘発するため、少量から漸増する慎重な管理が必要です。
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)に関しては他のページで詳しく解説しておりますので、是非チェックしてください。
診断と血液検査の活用
甲状腺疾患を疑う場面は、「説明困難な動悸・不整脈」「難治性脂質異常症」「原因不明の倦怠感や浮腫」といったケースです。
当院ではこのような場合は血液検査を初期スクリーニングに位置付け、TSH・FT4・抗体のチェックを行うことがあります。
例:
- • TSH 0.01未満、fT4高値 → バセドウ病を疑い、TRAb測定
- • TSH 10以上、fT4低値 → 明らかな甲状腺機能低下症、橋本病抗体チェック
- • TSH軽度上昇(5〜10)+ 正常fT4 → 潜在性低下症、心血管リスクと併せて治療介入を検討
血液検査の解釈は、単なる「正常・異常」の判定にとどまらず、循環器・代謝疾患の背景因子としてどう関与しているかを読み解くことが内科医の腕の見せ所です。
当院での甲状腺エコーの役割
甲状腺疾患の評価には超音波検査が極めて有用です。当院では外来で施行可能であり、以下のような意義を持ちます。
- • びまん性腫大:バセドウ病、橋本病の鑑別
- • 内部エコーパターン:橋本病では不均一・粗雑な低エコー像、バセドウ病ではびまん性高血流像
- • 結節の有無:悪性腫瘍除外(今回の主題からは外すが重要)
- • 治療経過観察:バセドウ病治療中の腫大縮小評価
血液検査だけでは判別困難な例でも、エコーを併用することで診断の確実性が高まり、また患者に「目に見える形で説明できる」という利点もあります。
腫瘍を疑う場合も実際に内部性状や詳細なサイズも測れるため、フォローをする際にも客観的に記録できるとこをも長所です。
治療の実際
- • バセドウ病:メチマゾールを主体とした薬物療法。動悸・頻脈に対してβ遮断薬を積極的に使用。心房細動が持続する場合は、抗凝固を含め循環器的管理を並行。
- • 橋本病(低下症):レボチロキシン補充療法。TSH基準で調整。糖尿病や虚血性心疾患を合併している場合は少量から漸増。
- • 潜在性機能異常:心血管リスクや糖代謝異常の有無に応じて介入を検討。特にAFや脂質異常症を伴う場合は積極的に治療対象とする。
まとめ
甲状腺疾患は循環器疾患・糖尿病・脂質異常症と密接に関連し、内科診療における「見逃してはいけない背景因子」です。特にバセドウ病は心房細動の重要な可逆的原因であり、早期診断・治療により心血管イベントを未然に防ぐことが可能です。
当院では、血液検査と甲状腺エコーを組み合わせた包括的評価を行い、循環器疾患や代謝性疾患の背景に潜む甲状腺異常を拾い上げ、適切な治療へとつなげていきます。
また、必要に応じて甲状腺疾患専門機関へのご紹介も行っておりますのでご安心ください。
- 1. American Thyroid Association (ATA) Guidelines Task Force. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016;26(10):1343-1421.
- 2. Bahn RS, Burch HB, Cooper DS, et al. Hyperthyroidism and other causes ofthyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association andAmerican Association of Clinical Endocrinologists. Endocr Pract. 2011;17(3):456-520.
- 3. Biondi B, Cooper DS. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. Endocr Rev. 2008;29(1):76-131.
- 4. Rodondi N, den Elzen WPJ, Bauer DC, et al. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA. 2010;304(12):1365-1374.
- 5. Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. Circulation. 2007;116(15):1725-1735.
- 6. Kahaly GJ, Dillmann WH. Thyroid hormone action in the heart. Endocr Rev. 2005;26(5):704-728.
- 7. 日本甲状腺学会. 甲状腺疾患診断ガイドライン 2018. 日本甲状腺学会, 南江堂.
- 8. 日本内分泌学会. 甲状腺疾患の診療ガイドライン 2022. 日本内分泌学会学術委員会.