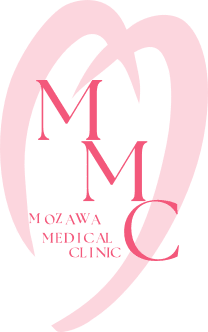アレルギー疾患とは?
アレルギーとは本来なら害を及ぼさないはずの物質に対して、私たちの免疫系が過敏に反応してしまう状態を指します。その代表がアレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、そして食物アレルギーです。現代社会では環境因子の変化(住環境の密閉化、大気汚染、生活習慣の欧米化など)と遺伝的素因が複雑に絡み合い、年々患者数が増加しているという報告があります。 厚生労働省の調査でも、花粉症を含むアレルギー性鼻炎の有病率は国民の約40%に達しており、まさに「国民病」と言える存在です。
私自身も重度の花粉症を持っており、小学校低学年から付き合ってきました。
春の季節は鼻水やくしゃみ、眼の痒みで生活の質や集中力はさがり大きな箱ティッシュを学校に持って行っていた記憶があります••
アレルギー症状に困っている地域の方々に少しでも内科医としてサポートできることを心掛けながら日々診療に当たっております。

茂澤 幸右
アレルギーの発症メカニズム
アレルギーの中心的な仕組みは Ⅰ型アレルギー(即時型反応) です。
- • アレルゲン(花粉、ダニ、ハウスダストなど)が体内に入る
- • 抗原提示細胞を介してIgE抗体が産生され、肥満細胞の表面に付着
- • 再度アレルゲンに曝露されると、IgEが架橋されてヒスタミン、ロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出される
- • 鼻炎ではくしゃみ、鼻水、鼻づまり、かゆみが生じ、喘息では気道収縮、皮膚炎では湿疹やかゆみを引き起こす
このように、免疫の「過剰防衛反応」が症状の正体です。
アレルギー性鼻炎の臨床像
アレルギー性鼻炎は 花粉症(季節性アレルギー性鼻炎) と 通年性(ハウスダスト、ダニなど) に分けられます。典型的な症状は三大症状と呼ばれる
- • くしゃみ発作
- • 水様性鼻汁
- • 鼻閉(鼻づまり)
です。これらは日常生活に大きな支障を与え、睡眠障害、学業・労働パフォーマンスの低下、さらに気管支喘息や副鼻腔炎の悪化因子となります。
特に内科医として強調したいのは、アレルギー性鼻炎が循環器や代謝系疾患に間接的な影響を与える可能性です。鼻閉による睡眠の質の低下は高血圧や糖代謝異常を悪化させることが知られており、軽視できない病態といえます。
治療薬の解説
治療は大きく分けて 薬物療法 と アレルゲン回避・免疫療法 に分類されます。
(1) 抗ヒスタミン薬
最も基本となる歴史のある薬。くしゃみ・鼻水に効果が強いです。第二世代抗ヒスタミン薬は眠気が少なく、内科外来で広く処方されます(例:フェキソフェナジン、ロラタジン、ビラスチン)。
(2) 抗ロイコトリエン薬
鼻閉に強い効果を示します。喘息治療薬としても使われるため、鼻炎と喘息の合併例には特に有用です(例:モンテルカスト)。
(3) 鼻噴霧用ステロイド
中等症以上で最も効果が高い治療薬。局所使用なので全身副作用は少なく、鼻閉改善効果も強力です。
(4) 点鼻用血管収縮薬
短期間は鼻閉を劇的に改善しますが、連用による薬剤性鼻炎に注意が必要です。
(5) アレルゲン免疫療法
原因となるアレルゲンを少量から投与し、体を慣れさせる根治療法。舌下免疫療法が広まりつつありますが、数年間継続する必要があります。
このように治療薬は「症状のタイプ」と「患者背景」で使い分ける必要があり、内科的な全身管理の中で最適化することが重要です。
ポイント:血液検査で自身のアレルギーを確認できる【View39検査の意義と解釈】
当院では View39(ビュー39) というアレルギー検査を導入しています。これは一本の採血で39種類の主要なアレルゲンに対する感作の有無を調べられる非常に有用な保険適用可能な検査です。
- • 吸入系アレルゲン(スギ、ヒノキ、ブタクサ、ダニ、ハウスダスト、カビ、動物の毛など)
- • 食物系アレルゲン(卵白、牛乳、小麦、大豆、甲殻類、ピーナッツなど)
がカバーされており、患者さんが「何に反応しているのか」を可視化できます。
解釈の際に重要なのは「陽性=必ず症状が出る」ではない点です。感作はあっても臨床的に症状がなければ過剰な生活制限は不要です。逆に症状があるにもかかわらず陰性の場合は、検査対象外のアレルゲンが原因か、非アレルギー性鼻炎の可能性も考えます。
内科医としては、患者の自覚症状とView39の結果を照合し、生活習慣や住環境改善の指導に結びつけることが肝要です。例えば「ハウスダスト陽性」であれば寝具の清掃、空気清浄機の活用、「スギ花粉陽性」であれば飛散時期の外出対策や薬の先行投与を行います。
View39は単なる「数値」ではなく、生活指導・薬物療法・免疫療法の方向性を決める「羅針盤」としての役割を果たします。
以下の方々には特に一度検査を受けることを推奨いたします。
- • 一度も検査を受けたことが無い小児・学生の方
- • 抗アレルギー薬を内服しても、症状が続いたり、薬をやめたとたん症状が再燃してしまう難治性の方
➤ 自身の体質を把握するという意味でも有意義であるといえます。 薬を長期的に服用するケースも多いと思いますが、肝機能や腎機能が上昇していないことを確認することも非常に重要であるため、当院ではケースをみて一般的な血液検査も行うこともあります。
まとめ
アレルギー性鼻炎をはじめとするアレルギー疾患は、単なる鼻や皮膚の病気にとどまらず、全身の健康や生活の質に大きな影響を与えます。治療は抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬、ステロイド点鼻薬を中心に、症状や生活背景に応じて組み合わせます。当院で実施しているView39検査は原因同定と生活指導に直結する強力なツールです。
- • 日本アレルギー学会:アレルギー疾患診療ガイドライン2022
- • Bousquet J, et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines. Allergy. 2020
- • Okubo K, et al. Japanese guidelines for allergic rhinitis 2020. Allergol Int. 2020
- • 日本耳鼻咽喉科学会:鼻アレルギー診療ガイドライン2021
内科医としては「症状を抑える」だけでなく、「患者の生活の中でどうアレルギーをコントロールしていくか」という視点を大切に診療を行っています。 お気軽にご来院ください!

茂澤 幸右